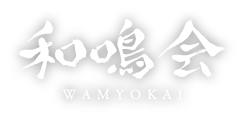雅楽からきた日常の言葉
雅楽の演奏技法や音楽用語などに由来して、現在の日常生活で使われる言葉があります
今回、雅楽からきた日常の言葉を五つ紹介します。
塩梅(あんばい)
○意味…物事の具合や様子また、程よい加減の時に用いられます。
一般的には、料理での塩と梅酢の加減からきたといわれています。
雅楽で古くから、篳篥の奏法に使われています。
同じ孔(穴)の音でも、吹き量や唇の位置を加減することで、音程に幅(高低やスラー)が出せます。
この奏法を「塩梅」(えんばい)といいます。
打ち合わせ
○意味…前もって相談すること、下相談することをいいます。
昔、京都・奈良・大阪(天王寺)には、それぞれ楽所(雅楽団体)があり、「三方楽所」と呼ばれていました。
それら三方楽人が奏楽のために一堂に召し出された際、微妙な演奏法を調整する為、前もって集まり、まず打楽器から約束事を取り決めたことによりできた言葉です。
なお、明治以後、三方楽人らが一つにまとまり、現在の宮内庁式部職楽部となりました。
楽屋
○役者などが化粧をしたり衣裳を着けたり、準備をする場所を楽屋といいますが、本来は雅楽の楽人の奏楽する場所でありました。
昔、庭に舞台を造る時は、楽屋は舞台のそばに仮設したり、回廊に幕をはり楽屋としました。
楽屋は、舞台より3間余り後に、横3間、奥行4間余りとし、前の方を管方の演奏する場所、後を屏風で隔てて舞人が装束を着ける場所としました。
楽屋は文字の通り音楽を奏する場所でした。
千秋楽
○意味…物事の終わり、芝居や相撲などの興行の最後の日のことをいいます。
後三条天皇か、近衛天皇の大嘗会に作られた曲です。
唐楽で盤渉調で後に黄鐘調にも移調されます。
舞楽法会などの最後には、この曲を演奏することが多かったようです。
相撲や芝居の最終日を千秋楽というのは、このことからきています。
ろれつが回らない
○意味…酒に酔い過ぎ、舌がもつれてうまく話せないことをいいます。
雅楽の旋法には、「呂」(ろ)と「律」(りつ)というものがあり、それぞれの音階に基づいて演奏されます。
その「呂」「律」の音階を間違えると訳の分からない曲になってしまうことから、「ろりつ」がなまり、この言葉ができたといわれています。
タグ:uru