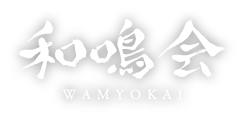紅葉の季節
長い猛暑の季節もようやく収まり、遅れていた秋が急速に現れ出しました。
その猛暑の影響か、農作物を筆頭に、季節の草木の成長も遅れ気味のようです。
秋は実りの秋と呼ばれるように、収穫の時期とされていますが、これまでの積み重ねが現れる時期とも言えます。食欲の秋です。
今年は、曼殊沙華が咲くのが遅かったと周囲は口を揃えていましたが、サンスクリット語で「葉より先に咲く赤い花」を表す言葉が「曼殊沙華」の語源と言われ、また仏教経典の中では「天に咲く花」という意味で「おめでたい事が起こる兆しに天から降ってくる花」と言われています。彼岸花と言われる花にしては私たちの持つイメージと反対の意味が込められていることに興味を惹かれます。
秋の収穫が一段落すれば、本格的な冬の季節に差し掛かるので、秋の季節の短さ・儚さを物悲しく捉える方も多いみたいですが、燃え盛るような紅葉の季節が始まったと思えば、物悲しさではなく、運動の秋・読書の秋、そして芸術の秋…心落ち着く貴重な時間を謳歌しましょう。
タグ:taka
雅~みやび~
今年のNHK大河ドラマ「光る君へ」では、度々雅楽が演奏されている場面を見かけます。
平安時代、貴族の生活の中で雅楽がどのような場面で演奏されていたのか垣間見ることができます。
奈良時代には、雅楽は主に儀礼や祭祀で演奏されていたのですが、平安時代になると天皇や貴族も楽器を演奏するようになりました。折りにふれて合奏をしたり、時には帝の前で演奏することもありました。楽器が演奏できることは貴族にとってステイタスであり、男女に関わらず大切な教養のひとつでもあったのです。
またドラマの中にも登場します紫式部が書いた「源氏物語」には、雅楽のことがよく出てきます。例えば最初の頃の段の中に「紅葉賀の段」と言うところがあり、その段の中で青海波という曲が舞われたことが出てきます。実際に現代にもその曲は存在し、舞もあり、古典文様としても有名であります。他にも、迦陵頻や胡蝶も出てきて当時から演奏されていたことを知ることができます。
そして清少納言の『枕草子』にも雅楽に触れた部分がいくつもあります。なかでも、清少納言が楽器の趣味について語った部分はよく知られています。『笛は、横笛、いみじうをかし。遠うより聞ゆるが、やうやう近うなりゆくもをかし。近かりつるがはるかになりて、いとほのかに聞ゆるも、いとおかし。』(笛は横笛がとてもよい。遠くから聞こえてくる音が少しずつ近づいてくるのも趣があるし、近くで聞いていた音が遠のいてかすかに聞こえるというのも、とても興がある)『笙の笛は、月のあかきに、車などで聞きえたる、いとをかし。』(笙は月の明るい夜に車の中などで聞くことができると、とても興がある) どちらも自然の情景に合わせて楽器の音色を楽しむ、平安貴族の感性がうかがえる文です。笛が近づき、また遠のいていく音色に耳をすませる感性は、現代を生きる私たちにとってもとても共感できます。
タグ:take
雅楽 楽家について
日本文化には、あらゆる領域に技芸を独占する家があり、その家芸の相伝が、いわゆる秘伝として伝承されてきました。例えば、歌舞伎・能・浄瑠璃などが思い浮かばれると思います。そのなかでも雅楽の家と秘伝は、最も典型的な存在であり十二世紀の中頃には、それぞれの楽家の家芸は、きわめてきびしく固定していたものと思われます。
そもそも楽家というのは、雅楽を伝承してきた家系で、京都方(宮廷・京都)、南都方(興福寺・奈良)、天王寺方(四天王寺・大阪)に属する雅楽家を三方楽人(さんぼうがくにん)と言われ、明治になって宮内省雅楽部が組織され三方楽所の楽家は東京へ移り、江戸幕府の紅葉山楽人と合流して宮内省雅楽部に編成され、現在は宮内庁式部職楽部として活動しております。
京都楽人安倍李尚があらわした『楽家録』に当時の三方楽人とその家芸が書かれています。
京都楽人 豊原家=笙、安倍家=篳篥、大神家・山井家=龍笛
多家=神楽歌・舞・和琴
南都楽人 東家・辻家・中家=笙、
上家・芝家・奥家・西京家・井上家=龍笛
窪家・久保家・北家=篳篥
天王寺楽人 薗家=笙・左舞、林家=笙・右舞
太秦姓東儀家=篳篥・右舞、安倍姓東儀家=篳篥
岡家=龍笛・左舞
このほかに、南都楽人に右舞だけを担当する右方人と呼ぶ、喜多・新・乾の三家と、寺侍藤井・後藤に二家があったようです。
江戸時代になると、三方楽所の楽人は上芸・中芸・次芸の三階級に分けられ、上芸・中芸の者には芸料が加給される仕組みでした。この階級を決定するのが三方及第あるいは楽講とよばれる全員参加型の実技試験制度でした。寛文五年(一六六五年)に始まり、慶応元年(一八六五年)まで特別な事情がないかぎり四年ごとに行われます。
楽講は、各回で調子を変えながら、壱越調・平調・双調・黄鐘調・盤渉調(天保以後は太食調も)の順に日を改めながら行われました。課目は三管(笙・篳篥・龍笛)のみで、助奏として鞨鼓・太鼓のみが演奏され、曲目はすべて左方楽(唐楽)であった。上芸・中芸のいずれを受験するかをあらかじめ決め、楽講が終わった後の入札で過半数を得れば及第である。入札は各方八名が自分の属している以外の二方の受験生に対して入札するものであるが、公平を期するために上芸者のうちその年に助奏をしなかったものが最終回の楽講の前に選ばれてさらに誓状を提出していました。試験当日になってくじ引きで曲目と演奏者の組み合わせが決定されるため、左方楽の全曲目について修練を積まねばならず、したがって楽講は雅楽の伝承と洗練に大きな役割を果たしてきました。
三方は地域別の流派のようなものであったし、その中でも家ごとに秘伝秘曲の伝承をする一種の家元制が行われていました。しかし三方及第はそうした流儀を越えて技を競い批評し合うシステムであったと考えることができ、これは日本の伝統芸能の中では特異なものであるようです。
タグ:uru
雅楽に暑さは大敵
梅雨明けと共に今年も暑い夏になっています。今年は史上最も暑い夏になるという話もあります。
さて、雅楽の楽器にとって暑さは大敵です。
笙という楽器は火鉢であぶって温めないと音が出せない楽器です。それはリードの接続部の蜜蝋を温めて柔らかくしないといけないからです。
かといってあまり温めすぎるとよくありません。高温になりすぎるとリードが壊れてしまう可能性もあります。夏の高温も要注意ですね。
龍笛も吹き口の中に蜜蝋が詰められいて、これで音程を調整しています。
この蜜蝋部分が変形してしまうと音が狂ってしまうわけです。
和鳴会のメンバーにも、かつて夏場の車内の高温で龍笛の蜜蝋が溶けてしまい大変な思いをした方もいます。
雅楽の楽器には暑さは大敵です。
舞楽の衣装も真夏の暑さの中ではとてつもなく汗だくになります。
タグ:dai
雑草という名の草はない
本格的に梅雨入りし、雨水を蓄えて草木が元気に育つ季節となりました。毎年、自坊が配っているカレンダーの六月の法語を紹介します。
ダンゴ虫には日傘なんだ
雑草と決めつけていたが
六月に入った今日この頃、田んぼや道の端などに草がたくさん生えてきているのをよく見かけます。私たちはそれを「役に立たない草」と決めつけ、雑草とよんでいますが、ダンゴムシにとってそれは自分のことを涼ませてくれる「役にたつ草」なのだということを教えてくださる言葉です。私たちが人やものを自分の都合によって「役にたつ」、「役に立たない」と分ける心を仏教では分別心といいます。このものごとを分別する心によって相手を傷つけ、そして自分自身も傷つけられているのが私たちではないでしょうか。
仏教の教えは、聞けば聞くほど自分の姿が見えてくる教えです。
これから各地のお寺で夏の法要が行われます。自分、世間の価値観を一度横に置いて仏さまの教えを聞いてみませんか。
タグ:masa