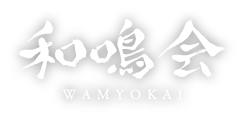雅楽の春夏秋冬
雅楽には、それぞれの季節にふさわしいとされる調子があります。例えば春は双調、夏は黄鐘調、秋は平調、冬は盤渉調です。
春にふさわしいとされる双調は、新芽の芽出しや若葉の息吹を思わせる明るく軽快な響きがあります。夏の黄鐘調は、太陽の強い日差しや生命力あふれる様子を表現しているとされ、力強く輝かしい響きがあります。秋の平調には、紅葉や収穫の時期を思わせる落ち着いた穏やかな響きがあります。冬の盤渉調は、冬の静寂や寒さを表現しているとされ、荘重で厳かな響きがあるとされています。

また、それぞれの季節をつなぐ調子として一越調があり、季節の変わり目にふさわしく、またすべての調子の中心となる調子とされています。これらの考え方は長い歴史の中で育まれてきたもので、日本人の独特な感性により生まれてきたといえます。私たちのご本山でも、主に4月(春)と11月(秋)に主要な法要がありその中で雅楽が奏でられますが、やはり季節にふさわしい調子や曲を選び、また法要の趣旨に合わせた曲を演奏します。
以前、「法要で演奏される雅楽なんてどれも同じに聞こえる」と言われたことがありました。確かにそのように聞こえるのかもしれませんが、心を静めて聞いてみると雅楽が持つ独特な雰囲気が、寺院という宗教空間と融合してなんともいえない幽玄な世界を表現してくれます。全部同じに聞こえても、実は調子や演奏される曲にはそれぞれに由来や意味があるということを忘れないでほしいと思います。
タグ:take