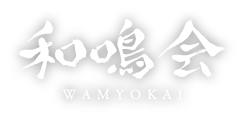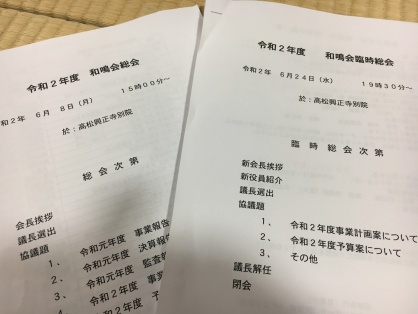新しい取り組みに挑んでいます!
例年であれば10月に和鳴会定期演奏会を予定して、今頃はその練習に励んでいるところですが、今年はコロナ禍の中、定期演奏会は延期となりました。その代案としてWEB配信を企画し、その撮影に取り組んでおりました。
残暑というには厳しい暑さが残る9月8日、さぬき市の野外音楽広場テアトロンで、管弦「越殿楽」と舞楽「陵王」の撮影を行いました。
リハーサルでは、暑さに負けそうになったり、本番では撮影用のドローンを、思わず目で追いそうになったりしながらも、野外ならではの、雰囲気のある映像が撮れたと思います。
また、9月17日には、各寺院の皆様に、和鳴会がお手伝い出来る一つの材料として、具体的に映像を見てもらえればと考え、これもWEB配信用に本堂での法要を撮影しました。
本堂では、カメラを複数設置しましたので、通常では見られない角度で法要がご覧いただけると思いますので、寺院関係に限らず、多くの方々に視聴していただきたいと思います。
配信時期は未定ですが、これをステップの一つとして、コロナ禍においても、様々なことに臨んで行きたいと考えております。
小豆島研修旅行
毎年恒例の研修旅行。いつもは一泊して交流を深めるのですが、今年はコロナの影響もあって、県外で一泊するのもなかなか難しいかということで、近場の小豆島に行ってまいりました。
私自身小豆島に渡るのは初めてではなかったのですが、10数年ぶりという事もあって、結構新鮮な気持ちで楽しむことができました。
今回は小豆島に着いてからレンタカーを借りて島内を巡って来ました。
二十四の瞳映画村・岬の分教場から、島でたったひとつの酒蔵MORIKUNIを見学。
そこで昼食をいただき、木桶が並ぶヤマロク醤油。オリーブ公園、エンジェルロードなどを回りました。
白いギリシャ風車やオリーブ畑など、日本の地中海と呼ばれる雰囲気と、島の持つ独特な空気感からか時間がゆったりと流れていくようで、いつもの日常とは違った時間を過ごすことができました。最近は、3年に一度開催される瀬戸内国際芸術祭などによって、瀬戸内の島々が色々と話題になっていますので、また機会があったら他の島にも行ってみたいなと思います。
終わりなき旅
先日うちの奥様が、大ファンであるMr.Childrenのライブを見ていたのを少し私も見ていたら、私の好きな曲を桜井さんが歌ってました。曲名は!「終わりなき旅」です。
閉ざされたドアの向こうに
新しい何かが待っていて
きっと きっとって 僕を動かしてる
いいことばかりでは無いさ
でも次の扉をノックしたい
もっと大きなはずの自分を探す 終わりなき旅
「終わりなき旅」作詞:KAZUTOSHI SAKURAI
という歌詞がとても好きです。
今年度和鳴会は、新しいチャレンジをします!とりあえずは、10月配信予定の演奏!雅楽の今ままでの見せ方と違った演奏をチャレンジします!
とにかく、新しく、楽しく、そして伝統を重んじた活動を行っていこうと思いますので、楽しみにお待ち下さい。
コロナ禍の新年度
和鳴会は6月に新年度を迎えます。三密を避けて行った、総会、臨時総会で活動計画、予算案の承認を受けて、新年度の活動が始まります。
ただ、「新しい生活様式」が言われている様に、和鳴会の活動も例年とは形を変えていかざるをえません。
例えば、毎年10月に高松興正寺別院の本堂をお借りして、たくさんの方にご覧いただいている「定期演奏会」も、今年は無観客でWEB配信の形をとって行う予定です。
WEB配信も、何が必要か分からず、手探りで始める感じです。上手くいくこともあれば、失敗もあるかも知れません。
コロナ禍の中、いろいろ試しながら、それを楽しさに変えて、取り組むこと全てにワクワクする気持ちを持って、会員一同、新年度を邁進したいと思います。
舞楽 陵王
舞楽の中では誰もが知っていると言っても過言ではないほど有名な舞になります。陵王は実在していた人物になります。
名前は「高 長恭(こう ちょうきょう)」中国の北斉の王族。眉目秀麗で戦場にて敵味方関係なく見惚れてしまう為、指揮が上がらず戦いにならなかったとか•••
そこで恐ろしい面を付け戦いに挑んだところ大勝を得、その喜びを表したのが舞楽陵王となったと伝われております。おめでたい席で何か舞をと言われれば、陵王となるほど定番の舞楽となっております。
ここまではどの雅楽会でも説明される内容です。
しかし大勝したその後を語られることはまずありません。
戦国の常と言えば治りつくのか分かりませんが、高 長恭は蘭陵王とは言ってもトップでありません。日本で言うなら征夷大将軍が上にいて、その将軍様に疎まれ始めます(高長恭の言動にも何かしらあったようです)。
そしてここで伝わるのが「賜死(しし)」で、これは褒美の一つだそうです。財宝に領地と言ったものと同じで「死」という褒美だそうです。私自身この話しを知った時には、祝いの舞じゃ無いとショックを受けました。舞楽を舞う者にとっては陵王を舞えると言うのは憧れでもあります。陵王を舞うときには、高長恭の栄枯盛衰、人の儚さを感じずにはいられません。
舞楽「陵王」の動画→こちら