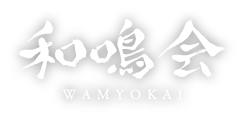除夜の鐘
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
私のお寺におきましても、大晦日に除夜の鐘を撞き、新年を迎えました。10年ほど前までは、近隣の方や御門徒の皆さま、友人知人が集い、108個のチョコレートを用意し、鐘を撞いては食べることを繰り返しながら、賑やかに除夜の鐘を撞いておりました。甘酒やぜんざいの準備など、手間のかかることもございましたが、夜遅くにお寺へ人が集う機会は滅多にないため、私自身も楽しみにしている行事の一つでございました。
しかしながら、コロナ禍以降、お寺にお越しくださる方は激減し、誠に寂しい限りではありますが、ここ数年は家族・親戚のみで鐘を撞いております。時代の流れとともに、大晦日の過ごし方も年々変化しているように感じております。
そのような中にあっても、古くから大切に受け継がれてきた宗教行事を後世へと繋いでいくため、家族揃ってお寺に足を運び、仏様に手を合わせ、一年間無事に過ごせたことへの感謝の気持ちをもって、除夜の鐘を撞きに来ていただきたいと願っております。
タグ:joe
「青海波」に寄せて ― 源氏物語の世界とともに舞った記憶
『源氏物語』紅葉賀巻にはこんな一節があります。
「源氏の中将は青海波をぞ舞ひたまひける…」
先帝の五十の賀にあたり、光源氏と頭中将が並んで舞を披露する、優雅で華やかな名場面です。
二人で舞う「青海波」は、舞楽の中でも特に気品高く、装束もこの舞のためだけに誂えられています。青海波文様に百余匹の千鳥を刺繍した袍、半臂、下襲、金帯、踏掛、そして太刀――。
まるで平安の雅がそのまま形になったような、格別の佇まいを纏います。
恥ずかしながら、私もかつて京都でこの「青海波」を数度舞わせていただいたことがあります。並びの位置は頭中将。紫式部が描いた美貌の貴公子にはとても及びませんが、それでも世界観を壊すまいと、当時の貴族であればどう舞うのか、どう息づくのかを想像しながら稽古に向き合っていました。
あの舞台に立つと、装束の重み、雅楽の音、舞台の空気――すべてが『源氏物語』の世界と静かにつながるような感覚がありました。観に来てくださる方の中には源氏物語ファンも多く、物語の一場面を現代に生きる私たちが受け継いでいるのだと思うと、不思議な責任感と幸せが入り混じったものです。
今思い出しても、あの時間は私にとって特別な宝物です。
タグ:touch
息づくご縁
11月9日(日)高知県にある真宗大谷派土佐別院にて報恩講(宗祖親鸞聖人のご命日)が営まれました。
いやいや、私たちは香川県在住。高知県とは同じ四国とはいえ格別に何かある訳ではないんです。きっかけは、お坊さん同士のやりとり。
土佐別院は普段は人の出入りが少ないお寺だというのですが、せっかくの報恩講、遠近各地から親鸞聖人のご遺徳を偲んで集う人々に何かしらの良い思い出なりとも…ということで、当会の雅楽を法要の中で奏でて欲しいとの依頼を頂いたという訳です。同じ浄土真宗のお坊さん同士、私たちも参集させて頂く運びとなりました。
雅楽を奏でる楽器・道具すべて持参です。太鼓・鞨鼓・鉦鼓・笙・篳篥・龍笛etc
コロナ禍以降なかなかないチャンス。楽しみに思い当日を迎えます。
見事に大雨orz
しかし、遅れるわけにはいきません。参加メンバーうち揃って、いざ高知へ。
道中の雨に先行きの心配を募らせながら、土佐別院到着。
雨は上がり、太陽が顔を覗かせます。
30人以上の参詣者が賑やかに参詣されるなか、雅楽器の説明を熱心に聞いてくださり、音色に感嘆の声を漏らし、大いに楽しんでくださった様子。
当会会長曰く「雅楽が法要に加わることにより法要の格式が上がる。」→「自分で勝手にハードルを上げてしまった…orz」か、会長…。
法要開始に伴い出勤僧侶の入場・作法・退場に合わせて平調の五常楽急・越殿楽・鶏徳・陪臚の4曲を奏楽させていただきました。
雅楽の演奏を間近で見ることが物珍しいこともあってか、参集の皆様が大変喜んでくださったことが嬉しく、普段、人のご縁が少ないというこの場所にも、親鸞聖人のご遺徳によって紡がれたご縁は確かに息づいていました。参加させてもらえたご縁に感謝。
タグ:taka
ちいさい秋見つけた
今年は例年にも増して長い夏でしたね。近日やっと朝夕涼しくなって、急に夏から秋への季節の移ろいを感じています。
先日、きれいな彼岸花を見つけました。仏花に彼岸花は使用できません。なぜなら毒が含まれているからです。仏花には、四季それぞれの花を供えますが、トゲのある花や悪臭のある花は避けるものとされています。しかし、水田や畑の近くに植えられているのは、虫やネズミ、モグラなどが毒を嫌って避けるようにするため、食物を守るためといわれています。毒のある花でありながら、その毒を活かして人々の役に立ち、またその美しさは人々を魅了します。花言葉は花の色によっても若干異なりますが、「また会う日を楽しみに」という花言葉もあるそうです。調べているうちに、心があたたかくなりました。
仏花にできなくても、別の花瓶に活けて、ぜひ秋を感じてみてください。皆さんはどのように秋を感じられているでしょうか?身の回りにちいさい秋はたくさんありますので探してみてくださいね。

タグ:maki
雅楽からきた日常の言葉
雅楽の演奏技法や音楽用語などに由来して、現在の日常生活で使われる言葉があります
今回、雅楽からきた日常の言葉を五つ紹介します。
塩梅(あんばい)
○意味…物事の具合や様子また、程よい加減の時に用いられます。
一般的には、料理での塩と梅酢の加減からきたといわれています。
雅楽で古くから、篳篥の奏法に使われています。
同じ孔(穴)の音でも、吹き量や唇の位置を加減することで、音程に幅(高低やスラー)が出せます。
この奏法を「塩梅」(えんばい)といいます。
打ち合わせ
○意味…前もって相談すること、下相談することをいいます。
昔、京都・奈良・大阪(天王寺)には、それぞれ楽所(雅楽団体)があり、「三方楽所」と呼ばれていました。
それら三方楽人が奏楽のために一堂に召し出された際、微妙な演奏法を調整する為、前もって集まり、まず打楽器から約束事を取り決めたことによりできた言葉です。
なお、明治以後、三方楽人らが一つにまとまり、現在の宮内庁式部職楽部となりました。
楽屋
○役者などが化粧をしたり衣裳を着けたり、準備をする場所を楽屋といいますが、本来は雅楽の楽人の奏楽する場所でありました。
昔、庭に舞台を造る時は、楽屋は舞台のそばに仮設したり、回廊に幕をはり楽屋としました。
楽屋は、舞台より3間余り後に、横3間、奥行4間余りとし、前の方を管方の演奏する場所、後を屏風で隔てて舞人が装束を着ける場所としました。
楽屋は文字の通り音楽を奏する場所でした。
千秋楽
○意味…物事の終わり、芝居や相撲などの興行の最後の日のことをいいます。
後三条天皇か、近衛天皇の大嘗会に作られた曲です。
唐楽で盤渉調で後に黄鐘調にも移調されます。
舞楽法会などの最後には、この曲を演奏することが多かったようです。
相撲や芝居の最終日を千秋楽というのは、このことからきています。
ろれつが回らない
○意味…酒に酔い過ぎ、舌がもつれてうまく話せないことをいいます。
雅楽の旋法には、「呂」(ろ)と「律」(りつ)というものがあり、それぞれの音階に基づいて演奏されます。
その「呂」「律」の音階を間違えると訳の分からない曲になってしまうことから、「ろりつ」がなまり、この言葉ができたといわれています。
タグ:uru